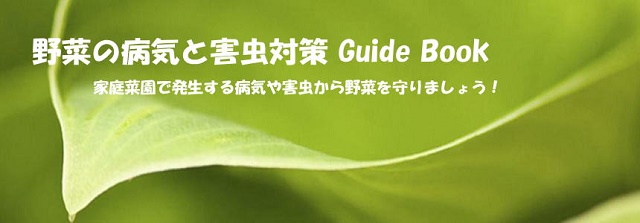つる割病の症状と対策 |
|
初期症状は、気温が高くなる時期に「日中に葉や茎が萎れる」「夕方以降に回復する」ことを繰り返します。 菌は根から侵入して根や茎の導管を通って株の上部へと移動しながら病気を蔓延させていきます。つる割病に侵された株の茎を切ると導管が変色しているのが分かります。 つる割病にかかりやすい野菜は、ウリ科の野菜で「きゅうり」「スイカ」「ゴーヤー」「メロン」「シロウリ」「トウガン」「マクワウリ」「ヘチマ」など。ウリ科以外の野菜では「サツマイモ」や「アサガオ」などに発生します。 |
|
つる割病を放っておくとどうなるの? |
||
更に放置しておくと、茎の基部から黄色く変色してヤニの様な汁が出たり、白色のカビが発生したりします。 治療をせずに放っておくと、病気の末期には根が褐色に変化して株が枯死してしまいます。 |
||
つる割病が発生する時期は? |
||
5月〜10月 つる割れ病は地温が20℃を超え始める時期の低湿度の環境ではウリ科の野菜によく発生します。 特に連作が多い畑では「つる割病」が発生しやすくなり、中耕や土寄せ時に他の株に感染することがあります。 また、塩類障害と株の残渣を残すこともつる割病の発生の誘引になります。 |
||
つる割病の発生条件と原因は? |
|
| 発病した畑の同じ場所でウリ科の野菜を連作すると、収穫を終えた株の残渣(ざんさ)の中で越冬した「つる枯病」の原因となる胞子が年を越してしまい、再び病気が発生してしまいます。 つる割れ病の原因菌は土壌の浅いところにいるので、切り取った発症した葉や茎を株元に放置したり株元の葉の茂り過ぎで日当たりが悪くなったりすると、そこで胞子が繁殖してしまいつる割れ病の発生原因となります。 |
|
つる割病を防ぐための予防と対策は? |
|
|
|
農薬を使わずに治療するには? |
|
| 「つる割病」は決め手となる薬剤はありません。治療するのが困難な病気なので抵抗接ぎ木苗を利用することが予防となります。早期発見を心掛け侵された株は迅速に対処し今以上の被害の拡大を防ぐようにすることが大切です。 つる枯病が発生した株は、発症部分を切り取って畑の外で必ず処分しましょう。その後は発生原因を追究して畑の状態を見直して再発を防ぎます。 つる枯病が株全体に発病した場合は、株ごと処分するか薬剤治療をするしか手立てはありません。薬剤を使用したくない方は、被害が大きくなる前に予防と対策をしっかりと行っておくことが大切です。 |
|
つる割病が蔓延してしまったら |
|
| つる枯病の初期段階の発症する葉の数が少ない時は葉を切り取ることで対策することが出来ますが、株全体に病気が蔓延してしまった時は、薬剤を使わないとなると株ごと除去するしか方法はありません。 マンションのベランダなどで数株を栽培している時は、株ごと抜き取る事は出来ないのでその時は薬剤を利用することを検討して下さい。 生育初期や収穫前であれば、決められた量と決められた回数を守って使用すれば人体への影響は少ないので薬剤の使用を検討してみましょう。 |
|
おすすめのつる割病治療薬は? |
||
カビが原因で起きる病気に効果があります。つる割病以外にも細菌やカビが原因の病気に幅広く効果がある予防効果と治療効果を兼ね備えた薬剤です。 耐雨性があるので効果が長く持続しますが、作物に対しての薬害の心配は少なく、人や家畜・動植物・ミツバチに対しても毒性が低い殺菌剤です。 病原菌が植物体に入るのを防ぎ、すでに侵入した病原菌を退治します。 |
楽天市場の取り扱いショップはこちら(クリック)
amazonの取り扱いショップはこちら(クリック) ![]()
Guide Book all rights reserved.